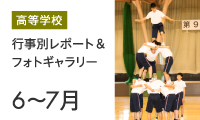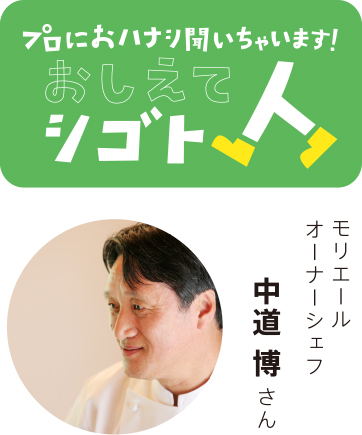
この春発売された「ミシュランガイド北海道」で三ツ星を獲得したモリエールのオーナーシェフ。ほかに4つのフレンチレストランを手掛ける。2008年の洞爺湖サミットでは、各国の首脳に料理を提供。2011年には農林水産省の顕彰である「料理マスターズ」に認定される。仕事に対する厳しさと優しい人柄で、スタッフからとても尊敬されている。開店当初から人気のじゃがいものグラタンは中道さんのオススメ。


建築物の建立や改修後には、棟梁の「サイン」を書き残すことが一般的であるけれども、飛鳥時代の大工のサインは残されていないので、誰がやったのかはわからないそう。ということは、褒められることもないってこと。飛鳥時代の大工がサインをしなかったのは「奉仕の心があったのはないか」と西岡さんは言っていました。「宮大工っていうのは褒められない仕事なんだ」ということをテレビで見て、それってすばらしいなって思い、室蘭の高校で受験勉強をしていた僕は、このとき「職人になりたい」と思ったんだ。褒められない仕事をやりたい、「努力しても褒められない」ってね。死んでから何百年もたった後に、「これをやったヤツは真面目によくやったんだな」って思われるような仕事をやりたいと思い『職人』になろうと思った。僕は宮大工みたいに器用ではないから、職人と言えば料理人があるなと思ったことかな。もう一つに「世界中いろいろと観てみたい」と思っていて、フランス料理をやったらフランスに行けるかなと思ったのが高校2年生でした。

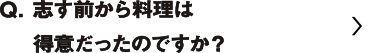

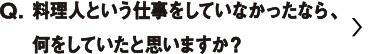

今だったら、そういうのがないと、ほかの人の責任にするじゃない。たとえばテニスをやっていたとすると「雨だから調子が悪い」といってしまうわけよ。でも『本当のテニス』をするとしたら、天気の善し悪し関係なく「天気を楽しみ、雨のときのテニスもおもしろい」となっていかないと。それには『器』みたいなのが必要で。今の時代はインターネットでいろんな情報を探れるけど、(自分の基準、自分の器がないと)選べないよ。人の言ったことをただ受けるだけではまるで「人形」だよ。「あいつはこう言うけどオレはこういう好みだ」ということ。
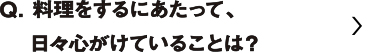
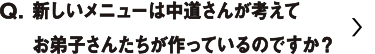

![]() 食感にもびっくり!甘くておいしいナスと洋なしのデザート
食感にもびっくり!甘くておいしいナスと洋なしのデザート

![]() 居心地の良い季節感のある店内
居心地の良い季節感のある店内
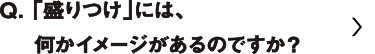
イチョウで言うならば、葉っぱが2枚あるけど、葉っぱは1枚になり、葉の軸が残り、葉先になり、そして風になるかもしれない。そうなると、見る人は風がヒューッとなっているのを見ると、イメージでイチョウに木から葉っぱが落ちる…、そこに黄色があるとイメージがもっと広がる。そういうもんで、やってれば自然にできる。
盛りつけはイメージしなくても勝手にできる。わかる?要するに、きれいに盛ろうと思ってもダメ。普通に盛ってもきれいになる。問題は「何がきれいと思うか」。かぼちゃがテーブルにこんなふうに置いているけど、このかぼちゃが「あ~きれいだな」と思うかどうか。たとえばこのかぼちゃを「磨く人」もいれば、わざと「泥をつける人」もいたり、「おがくずを入れる人」もいる。いろいろいるさ。それが美意識っていうものさ。
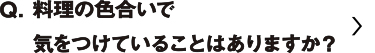
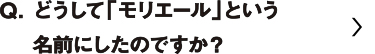
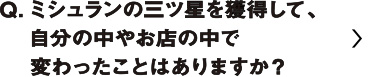
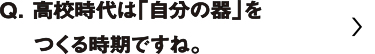
僕には今22歳になる息子がいるけど、当時の僕と同じように料理人をめざす環境にいるんだけど、勉強そんなに好きじゃないみたいだから、「部活は卒業までちゃんとしろ」って言ってた。そしたら大学受験できないからね(笑)。彼が高2のときに、僕が「いいな」って思っていたCIA(The Culinary Institute Of America)という料理の学校がニューヨークの郊外にあって、「おまえはそこに行け」って言ったら「はーい」なんか言っちゃって。勉強しなくていいからせいせいしたのかな(笑)。ギター好きでギタリストになりたいって言ってたけど、ギター弾けたからギタリストになれるわけではなく、どういう感性を持っているかだよ。さっきの『器』だね。同じものみても、きれいさが違う。その「きれいさ」がちゃんと分かるような自分の資質をつくらないと、速くギターが弾けたからといってダメなんだ。
高3の夏になると、部活の大会も終わり暇になるから英語の勉強してさ、「偏差値で大学行くなら行くな」と言った。CIAはTOEFL(Test of English as a Foreign Language)で80点をとらないと入れなく、最初は22点。でも、1年半勉強して入学した。だから、人って頑張ればできるんだよ。1日16時間ぐらい死ぬほど勉強していた。そして2年でその学校を卒業し、その後もまだ勉強するといってスイスのローザンヌのホテル学校に行くと言って、ハードル高くして今も勉強しているよ。
職に就くには、なんかきっけかがあるんだよ。なんか「引っかかるもの」を待っていたらいいんだよ。そのためには広く興味を持っていたほうがいいのではないかな。
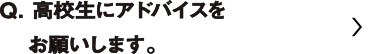
今は高校生だから定期試験や入試などそれに向かって頑張るでしょ。たとえば大会があれば、それに向かってやるでしょ。ところが大人になったら、そういう試合とかがないのさ。じゃあ、何を目標にするかというと、毎日の積み重ねなんだ。誰も自分を選ばないし、そういうところには向かわない。目標設定値がないの。ではどこにあるかっていうと,自分の中にしかない。
会社には組織があるよね。今ここにグラスがある。この上に蛇口があって、そこから水がぽとぽと落ちてくる。人が一生懸命働いていると、この落ちてくる水は「才能や努力」などといったいろんないいもの。水がいっぱいになるとグラスから溢れてしまう。それがもったいないから「受け皿」を用意する。その受け皿が組織の最初であるんだ。その受け皿にも水がいっぱいになると、もう一皿。それ(組織)がだんだん大きくなると、形だけを作る人がいっぱいになる。問題はぽとぽと落ちる才能などがあるのか?ってこと。受け皿の形を作っているだけではないのか?グラスは『器』。つまり『自分』。水は自分の才能など。形だけをつくってやるのではなく、溢れ出るのなら受け皿(組織)を用意しなさい。若いあなた方は、この水はどんどん流れあふれ出る。働けるし動ける。僕らみたいになると、すかすかになり水はぽとぽと。歳を取ってもぽとぽとでも落ちるように努力することが大事なんだ。だから、55~60歳のときには、たくさんの今までやったことないこともやった。イヤなことだって。そうすると、再びいろんなことが沸いて出るようになった。だから、さっきの「メニューはどうやって考えるのか」なんてのも「自然に出ます」ってことなんだ。前は自然と出てこなかった。蛇口と一緒で、そのときは「出さないと出てこなかった」が、今は湧き水のように出てくる。そしてお客さんに喜んでもらえる。でもあと2年たったら、スカスカになるかもしれないから、今、努力している。この先のために。そんなことなんだよ。
うちの子どもに勉強させようと思ったのは、そいういことを学問として学んで料理してほしいと思ったから。僕らはそういうことを感覚で覚えている。汗水流して悩んでやってきて。だから、あなた方は若い世代であって次の時代なんだから、もっと勉強して知識をつけて学問として入れながら汗水流していけば、僕らよりももっと良くなる。そうやらないとすばらしい人生なんかは送れないと思うよ。
コックさんの話をすると、フランスですごく優秀な人はみんな20代~30代前半。若い人は頭が良くとらえ方がすごく上手で料理もすばらしい。ぼくにはできない。だから、自分の年代でできることを目指している。人はものすごい進化している。僕の時代は生活も貧しかったから、汗水流してやって技術力を上げていった。でも今はすごい優秀な人とそういう所に気がつかない人がいる。その差がすごく感じる。優秀な人っていうのは、特殊かというとそうではなく「気がつける人」だと思う。真面目なんだけど遊ぶこともできる。僕らはほかものも切り捨て24時間やっていた。若いうちから興味を持って好きなものを仕事のほかにも持っていくことで感性が膨らむんだよ。だから若いみんなには、勉強以外にもスポーツでも美術でも音楽でも何でもいいから。だから自分で「すばらしい人生だったな」って思える毎日を積み重ねてほしい。目標設定値は自分の中にある。だから自分の価値観が大事。小さくていいから、最初から大きいわけでないんだから、しっかりとした『器』を作っていく。歳を重ねるごとに、自分の『器』が少しずつ少しずつ大きくなっていけばいい。

お年寄りを招いてね。歳を取ったら、あんまりこういうもの(フランス料理)を食べる機会がないでしょ。お漬け物や納豆とごはんぐらいしかおいしいなって思わなくても、フランス料理を食べてシャンパンでも飲んで、こざっぱりとした格好をさせてさ、お婆ちゃんが僕の料理を食べて「フランス料理って、大したうまいもんじゃないな」って言いながら食べるシーンをやりたいね。そのお婆ちゃんが家に帰って家族でしゃべって、「大したもんじゃないな」とか「なかなかいもんだね」なんて言ってくれてさ、1年たっても、5年たっても、もしかしたら死ぬまで、「料理を食べた思い出がずっと生きてくれるんじゃないかな」って、そういうレストランができたらいいなって。だから「想い出レストラン」って言っているわけ。それをボランティアでやりたい。だって、このような料理って結構高いじゃん。収入があるときは食べれるけど、なくなったら食べれないわけだから、誰かの役に立って、食べてもらって話のネタになりたいなっていうのが夢かな。やりますよ。
もう一つは寺子屋みたいのをやること。料理人の勉強の場。料理人は一生懸命やっているけど、教育が足りないんだ。そういう教育施設ができればいい。それをやると就職がいいとか偉くなれるとかではない。「人に喜んでもらいたいなって思う料理人がたくさん現れたらいいな」って思っている。2015年、美瑛に誕生させます。「2015年小麦畑の中で…」薪釜でパンを焼いて、料理はプロバンス地方の家庭料理をやれたらいいな。興味のある人は是非来てください。
僕は以前、ある道南の小学校で課外授業をしたことがあるんだ。「隣の人と競争するのではなくて、もっと広くものを見てもっと違いで判断するべき」という話をして、子どもたちの話を聞いているうちに、食についていかに貧しい環境にあるかが分かり、モエレの店に招いてフランス料理を振る舞ったことがある。僕はそのとき「先生の醍醐味」っていうのも感じたよ。みんなも、是非、僕の料理を食べてみてよ。
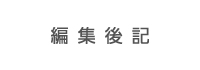 |
とてもお忙しい中、私たち高校生の質問に真摯に答えてくださり、料理までふるまってくれた中道さんとシェフの今さん、そしてお店のスタッフのみなさんの優しさに心から感動しました。料理の一つ一つからも私たちのことを考えてくださっているのが伝わり、「お客さんを喜ばせたい」という思いを感じました。特に、ナスのデザートはおいしさだけではなく楽しさと驚きがありました。スタッフの方々のお話をお聞きして、「何をするにも一人ではできない、チームワークが大切」ということも学びました。本当に貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。 |
|---|

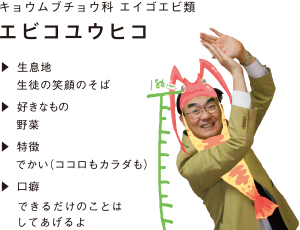

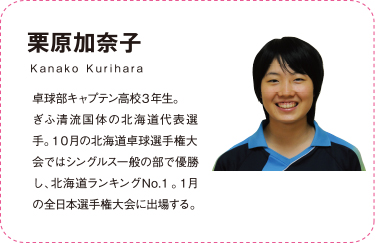
たくさんの支えに感謝
卓球を始めたのは小2のとき。体が弱かったので体力をつけるためだったそう。中1から大谷の卓球部に所属。6年間つらいこともあったが、自分のために泣いてくれる、怒ってくれる、喜んでくれる仲間と指導者の方々の中で過ごすことを通して、支えてくれている人に感謝することの大切さを一番学んだという。
卓球が好き
10年以上も続けてくることができたのは、「卓球が好き」という気持ちがあったから。元気の源は「食べること」。特に「米」。いやなことがあっても、食べて忘れているそう。
一本の重み
これまでに何度も全国大会に出場する中で、「勝つためには技術だけではなく、最後の一本をとれる『人間力』が必要」と感じるそう。
力強い目標
いくつかの質問に笑顔で答えてくれた栗原さん。これからの目標は、「大学でも卓球を続け、全日本学生大会で優勝すること。そして、団体戦ではレギュラーとしてチームに貢献すること」と力強かった。目標を常に心にとどめており、それが彼女の活躍につながっているのだと感じた。

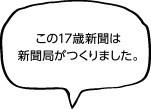

 モリエール
モリエール